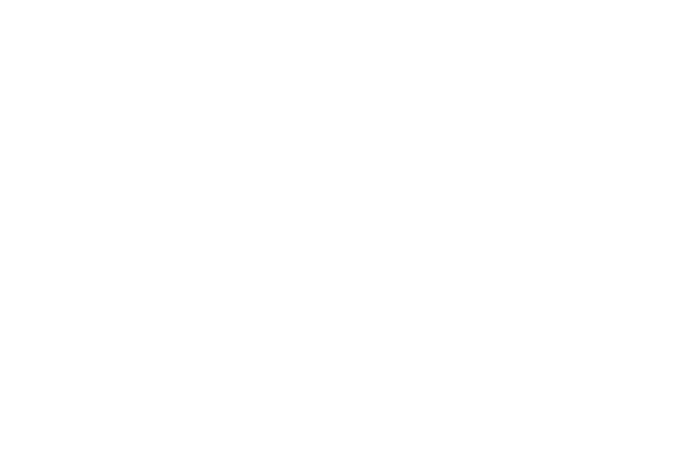前田 太郎 (基礎生物学研究所)
ウミウシ類の一部の種は、餌海藻の葉緑体を腸壁の細胞内に取り込み光合成を行う。本現象は盗葉緑体現象(Kleptoplasty)と呼ばれ、動物細胞中で光合成に必要なタンパク質をどうやって確保しているかが議論されている。一方で、本現象の適応的な意義については未だ不明確なことが多い。古典的には、光合成から栄養を得る事で、1)ウミウシが餌探索にかけるコストを減らすことができる 2)餌海藻が少ない季節を乗り越えることができるなどが考えられてきた。しかし、野外のウミウシが光合成にどれほど依存しているかは不明確であった。そこで私達は、特に長期間(10ヶ月ほど)光合成活性を維持するチドリミドリガイ(Plakobranchus ocellatus)を用いて、野外のウミウシの摂食頻度と光合成への依存度を明らかにしようとした。具体的には、窒素安定同位体比を用いて野生個体の栄養段階を評価し、さらに絶食状態で飼育した場合の生存日数を、明暗条件下と暗黒条件下で比較した。結果、栄養段階を反映するアミノ酸中の窒素安定同位体比は、1次生産者より植食者に近い値をとり、野生個体は光合成よりも摂食からの栄養に強く依存していることが示唆された。さらに体内の葉緑体の季節変化もこの結果を支持した。一方、絶食下での生存日数は、明暗条件で飼育した方が暗黒条件よりも有意に長くなり、光合成によって生存日数が延長されることが示唆された。以上から、ウミウシは餌がある場合は摂食を頻繁に行い、餌が少ない状態では光合成に依存する生活を行っていると考えられる。盗葉緑体現象は餌海藻が少ない季節を乗り越えるのに有利な形質と考えられる。